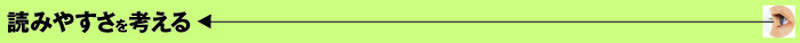
荒瀬光治
1――読みやすさの研究と出版文化の継承
|
かつて一定量を超える分量の「文字を読む」行為は書籍・雑誌・新聞という広い意味での出版の世界の話でした。ところが産業構造の変化にともないチラシ・カタログ・パンフレットなどの商業印刷物にも見る行為だけでなく読む要素も増えてきました。また、情報機器の進化にともない携帯・パソコンなどでも日常的に「読む」という行為は行われるようになりました。
その「読む」ための書体選定や字詰や行間を決める、つまり組版の指示のための作業を行う職業にデザイナーがいます。かつて出版ではレイアウト用紙という各段組ごとの組版フォーマットを印刷したものがあり、その上に個別の誌面デザインの設計図を作成し、印刷所で版下やデータを作ってもらっていました。このレイアウト用紙は経験を積んだデザイナーが作成するため、新人デザイナーが作業しても、このフォーマットを使う限りは「読みづらく」なることはありませんでした。それが新人が継承する「読みやすさ」の基本にもなりました。 |
日本における印刷物の可読性の研究は大正時代から行われています。東京築地活版製造所の社長、野村宗十郎が東大の桑田芳蔵博士に、活字の書体や大きさ、行の長さ、語間行間の広さ、行の配列方法や余白の分量など 21 項目にわたり心理学的研究を依頼しています(今井直一『書物と活字』)。
印刷の歴史は、ある意味では「活字」による「読みやすさ」を追求する歴史でもありました。活字のデザイン、組版(縦組・横組、字詰と行間)の問題、インキの色と紙の色など、印刷所や研究機関ではさまざまな面で研究がなされ、それが出版物の文化としても継承されてきました。それらの蓄積の上に経験を積んだ編集者やデザイナーの作業がありました。 ところが DTP の普及とともに、印刷所が組版を行わなくなり、預かったデータを出力・印刷することが印刷所の仕事となりました。さまざまな面での「読みやすさ」の判断は、文化の継承を考える余裕もなく、ともすると一人の DTP 担当者やデザイナーにゆだねられるような状況になっているのが実情です。 |
「ページ印刷物〜」トップへ 「読みやすさ」トップへ 次(2)へ
このホームページに関する、ご意見・ご感想は mailto:arase@mbe.nifty.com までemailをお願いいたします。